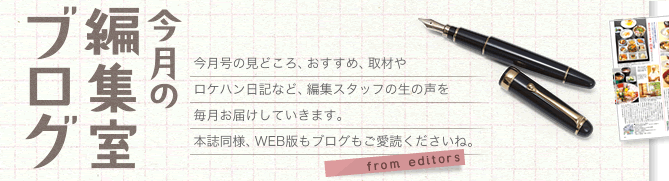
寒さが厳しかった今年の冬、そしてオミクロン株の感染急拡大。なかなか気持ちも落ち着かない毎日ですが、2月になって日差しはゆらゆらと明るく、植木鉢の水仙も小さな芽を出しました。ちょっとうれしい休日、4月号の週末クッキングで奥野シェフに教わったローストビーフに挑戦! やっぱり人間、好きなことするのが、いちばんの元気のもと! 私の場合は食べる、つくる、そして食関連の本を読む。年を経てますます「食」への興味に、一極集中です(笑)。
まずは、住吉駅直結のシーアにて、鹿児島産和牛もも肉380gを購入!約2800円也。材料は、肉と塩こしょうのみのシンプルさ。中心温度をしっかりと測りたいので、調理用温度計も購入しました。

厚みもあるもも肉を購入。

たこ糸をかけました。

塩こしょうはしっかり目に、全体にまぶします。

フライパンで、肉の表面をていねいに焼きます。

オーブンは、予熱140℃に設定。

天板にホイルを敷き肉をのせて、下段で20分。

温度計を差し込むと、64℃に!(58℃以上ならOK!)

すぐアルミホイルで包み、粗熱が取れるまでそのままおく。
肉汁が落ち着き、冷めてから切ると、きれいな肉の色!
肉は、薄く薄く切って、トーストしたパンに、粒マスタードやピクルスなどと一緒に、たっぷりはさむのがおすすめです。
また、辛子じょうゆや、みりんとしょうゆを同量で軽く煮立てたタレで食べるのも◎。ごはんにも合うおいしさ。うすーく、きれいに切るのがコツです。
本棚に、ズラリならんでいるのが、食にまつわる本。背表紙を見ただけで、この本のアレがおいしそうだったなー、と思い出が甦る。そこで、かなり大昔の本ばかりですが、食の楽しさを目覚めさせてくれた、目からウロコの本を引っ張りだしてみました。作家、映画評論家など、本業以外の人の食エッセイはさすが!の一言。
『檀流クッキング』
昭和45年サンケイ新聞出版局刊

作家檀一雄さんが、「この地上で、私は、買い出しほど、好きな仕事はない」とばかりに、世界中を旅して、市場を回り、その土地のものでつくって食べた体験を元に、中国のモツ料理からフランスのオニオングラタンスープ、ロシアのボルシチ、宮崎のヒヤッ汁など、読めば作ってみたくなる料理のオンパレード!
『女たちよ!』伊丹十三
昭和43年文芸春秋刊

私にとって、まだ見ぬヨーロッパの、食べ物にまつわる本物の話を次々に繰り広げてくれて、目の前がパッと開けたように感じた本。歯切れのいい伊丹十三の文章に引き込まれながら、その博識ぶりに目からウロコ。目玉焼きの正しい食べ方、には笑った記憶が。
『巴里の空の下、オムレツのにおいは流れる』石井好子
昭和48年暮らしの手帖社刊

「おいしいものというのは、なにもお金がかかったものではなく、心のこもったものだと私は信じている。この本にはいろいろなお料理のことを書いたけれど、私のおいしいと思うものは、銀のお盆にのったしゃれた高価な料理ではなく、家庭的な暖かい湯気のたつ料理だ。台所から流れるフライパンにバタが溶け卵がこげてゆく匂い、それは台所で歌われている甘くやさしいシャンソンではないだろうか」(あとがきから)。パリでのていねいな暮らしぶりに、こちらの心も温まる。
『男のだいどこ』荻昌弘
1972年文芸春秋刊

最初の章の、「君子、厨房に入る」のところから一気に流れ出す、痛快な文章に引き込まれる。通ぶって高級な店の自慢話をひけらかし、自分で料理をつくることを考えない「君子、厨房に入らず」ではなく、全国を旅して、その土地のうまい料理を食べたあとは、<なんとかそれを自宅でヒョウセツ盗用できないか、と、せまい台所で工夫を重ねること>が、楽しみという、映画評論家の食談義。「コロンブスの瓢亭卵」<半熟卵を黄身を流れ出さずに、二つに切って立てる、京都の瓢亭の名物の卵>の項ではその成功談も!
『吉兆味ばなし』湯木貞一
昭和57年暮らしの手帖社

暮らしの手帖の花森安治氏が、吉兆の湯木貞一氏に取材してまとめた本。日本料理と日々向き合う湯木氏の言葉の数々は、季節を尊び、日本の文化や美意識を尊ぶ心にあふれていて、日本の料理の豊かさを再認識させられる。料理屋の仕事を語り、ご家庭ではこんなふうに、と日常の食事の大切さを優しく説いてくれる言葉にも、美意識が感じられて気持ちがシャキッとする。
(Y・Y)
★4月号のブログの更新日3月10日です。
★編集室スタッフ5人が交替で登場します。お楽しみに!
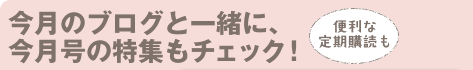

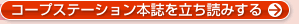
2022年3月号

